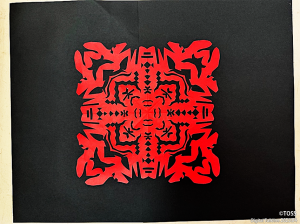2025年4月号(QRコード・SNS用)
- 3月
- 17
25年 4月号
デジタル・トークライン
<CONTENTS>
1.[特集]:「黄金の3日間」のスマート開始術
学級が「日に日に楽しくなる」システムを公開
柳町 直先生・橋本 諒先生・工藤孝幸先生・水本和希先生
本澤 航先生・田中泰慈先生・堂前直人先生・長谷川博之先生・林 健広先生
2.大成功の絵画工作指導
佐藤昌彦先生
3.本誌掲載論文の関連カラー画像
菅野祐貴先生・林 健広先生・千葉雄二先生・川原雅樹先生・塩谷直大先生
本澤 航先生・原地信久先生・武井 恒先生・赤塚邦彦先生・
橋本 諒先生・水本和希先生・吉永順一先生・師尾喜代子先生・美崎眞弓
4.トークライン本誌PDFデータ
5.向山洋一の言葉から学ぶ教育実践~「向山洋一映像全集」より~
6.谷編集長の5min.アンサー
7.高段者が答える「私が困っていることQ&A」デジタル版!
林 健広先生「 4、5月は成功体験させる 」
8.今月のサークル紹介動画
9.教育コミュニティコンテンツ
《2025年5月号のお知らせ》
2025年5月号のデジタルトークラインは2025年4月15日公開予定です!!!!
●データで確認! 本誌カラー資料&PDF●
1.[特集]:「黄金の3日間」のスマート開始術
~学級が「日に日に楽しくなる」システムを公開~
子供との信頼関係を安定させる仕掛け:
3日間で全員の名前を呼んで褒めた場面【GIGA併用】
①全員を褒めたことを記録しておく
柳町 直先生
本誌17ページの関連資料をカラーでご紹介します。
子供との信頼関係を安定させる仕掛け:
授業中のコメントを保護者に伝える【GIGA活用】
②情報は、動画が一番よく伝わる──8秒動画を保護者に公開する
橋本 諒先生
本誌18ページの関連資料をカラーでご紹介します。
子供との信頼関係を安定させる仕掛け:
授業中のコメントを保護者に伝える【GIGA活用】
③つながる教室、つながる家庭
工藤孝幸先生
本誌19ページの関連資料をカラーでご紹介します。
学級生活の仕組みの指導
④「係」と「当番」の違いを具体的に教える
水本和希先生
本誌20ページの関連資料をカラーでご紹介します。
学級生活の仕組みの指導:
「係」と「当番」表の作り方・掲示の仕方【GIGA併用】
⑤係と当番はCanvaでおしゃれに作成!
本澤 航先生
本誌21ページの関連資料をカラーでご紹介します。
QR画像

学習の仕組みを安定させる:
カレンダーとタスクで予定を共有・可視化する【GIGA活用】
⑥Googleカレンダー・タスクで「何をするのか」「いつするのか」
子供、保護者と共有する
田中泰慈先生
本誌23ページの関連資料をカラーでご紹介します。
学級生活の仕組みの指導:
ノートの使い方の基礎・基本を教え、定期的にノートチェックをする
⑦きれいに書かれたノートが、子供の力を伸ばす
堂前直人先生
本誌24ページの関連資料をカラーでご紹介します。
学級が「日に日に楽しくなる」私の仕組みづくり:
1年間安定する学習ルール・しつけの教え方
⑧説得力のあるルールを、説得力のある授業で
長谷川博之先生
本誌26ページの関連資料をカラーでご紹介します。
学級が「日に日に楽しくなる」私の仕組みづくり:
2・3学期につながる4月からの布石指導
⑨教師は1年間、笑顔をキープする
林 健広先生
本誌27ページの関連資料をカラーでご紹介します。
2.大成功の絵画工作指導
世界最古の折紙の本と 一枚の紙でつくる模様
佐藤昌彦先生
本誌4、5ページ掲載の佐藤昌彦先生の関連画像をカラー画像でご紹介します。
解説は本誌をご覧ください。
3.本誌掲載論文の関連カラー画像
写真で解説!一目でわかる指導のコツ
子供が変わる! 授業が変わる! 超凄腕 板書術・ノート術
①算数の授業が楽しくなる 黒板マネジメント
菅野祐貴先生
本誌2、3ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。
●国算 現在進行形の教科書単元 すぐに追試できる開始15分間の発問
②とにもかくにも、子供を褒めよう!
≪1年算数≫ 林 健広先生
本誌28、29ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。
<引用>
『歩きはじめの算数: ちえ遅れの子らの授業から』(遠山啓編/国土社)
『通常学級で役立つ算数障害の理解と指導法』(熊谷恵子・山本ゆう著/学研)
QR画像

●国算 現在進行形の教科書単元 すぐに追試できる開始15分間の発問
③扉の詩でパロディ詩をつくろう
≪6年国語≫ 千葉雄二先生
本誌38、39ページ掲載の関連画像をご紹介します。
「基礎・基本の授業例」と「主体的・対話的で深い学びの授業例」
④○基礎・基本
「なぜ野辺山高原はレタス生産日本一になったのか」①
○主体的・対話的で深い学び
「なぜ野辺山高原はレタス生産日本一になったのか」②
≪5年社会≫ 川原雅樹先生
本誌40、41ページ掲載の関連画像をご紹介します。
新学習指導要領対応 道徳・英語・オンラインの授業実践
子供たちがICTを文房具化するワザ12アプリの活用方法
⑤1年生でもできる!ホワイトボードアプリ「FigJam」を普段使い
塩谷直大先生先生
本誌44ページ掲載の関連画像をご紹介します。
QR画像

新学習指導要領対応 道徳・英語・オンラインの授業実践
学びを進化させるヒント:子供主体の探究とICT活用
⑥端末のルールを可視化させ、学習環境を整える
本澤 航先生
本誌45ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。
特別支援教育 専門家の視点 &
全国で大人気“特別支援教育の指導システム”
医師・研究者の目から見た特別支援教育
⑦「先生は僕にとって信頼できる」
本誌50ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。
特別支援教育 専門家の視点 &
全国で大人気“特別支援教育の指導システム”
プロが教える教室でできる手づくり教材
⑧棒(カラーバー)トレーニングの提案
武井 恒先生
本誌53ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。
QR画像


授業が激変!TOSS指導法
クラス全員が熱中するこの教材!
⑨初めての漢字テスト一〇〇点
赤塚邦彦先生
本誌54ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。
働き方改革!教師が「やりがい」と向き合うために
学年別 すぐに使える学級経営のポイント 低学年 中学年 高学年 中高
⑩当番活動を定着させて学級を安定させるポイント3
橋本 諒先生
本誌56ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。
掃除動画

働き方改革!教師が「やりがい」と向き合うために
仕事に役立つこのアプリ!時間短縮の仕事術
⑪「ビジュアルなお知らせ」をCanvaでデザイン!
水本和希先生
本誌57ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。
授業技量向上の法則
向山洋一が学んだこの1冊!
吉永順一の読書論
⑫校長は学校で何をしているのか
吉永順一先生
本誌64ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。
『マネジャーの仕事』(ヘンリー・ミンツバーグ著/白桃書房)
「永池校長に学ぶ」(冊子『ひとりだちの力を』所収)
人気ライター トークラインだけの裏話
となりの座席の女発社長奮戦記
⑬1日のルーティン穏やかな毎日
師尾喜代子先生
本誌72ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。
人気ライター トークラインだけの裏話
向山洋一の日常から学ぶ仕事術
⑭1997年から始まったTOSSの社会貢献活動
美崎眞弓
本誌73ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。
4.トークライン本誌PDFデータ
本誌全ページのPDFデータがダウンロードできます。
2021年4月号からスマホで見やすいように1ページずつのレイアウトに変更しました!
(本誌と一部のフォントが異なります。
また、画像の解像度を低く設定しています。ご了承ください。)
閲覧・検索にどうぞご利用ください。(印刷はできません。)
こちらをクリックしてください
➡TL202504_web
●デジタル版だけの特典! 動画コンテンツ●
5.向山洋一の言葉から学ぶ教育実践
~「向山洋一映像全集」より~
子供を育てる第一歩である
「情報読解の指示の源流」
映像全集第四巻「わたしたちの国土と地球」の授業。
「情報の収集」の最高峰を見る。
写真を貼って十五秒後。向山氏はこう指示する。
「写真を見て、気がついたことを、ノートに箇条書きにしてください。」
子供たちはその後八分間、写真の前に集まり、ノートに箇条書きをしていく。
その後発言する子供たちの発表も異次元だ。
「こんなにゴミがいっぱいあるんだから、フロンガスがいっぱい出るんだと思う」
「あと二、三年でこの島からゴミがあふれると思う」
いきなり未来予測。
ここに至るには、日頃の授業で子供を鍛える必要がある(詳しくは映像全集で解説されている)。
探究型の授業で行われる、「情報の収集」。
方法論だけではなく、能力育成の必要性に気付かされる。
また、情報をうのみにせず、批判的に検討する姿は、
文科省が示す「新たな価値を創造する力」にほかならない。
出典:「向山洋一映像全集」第四巻「わたしたちの国土と地球」の授業 より
【デジタルチーム:平野遼太】
本編全てを見たい!という方はコチラ→
お申込み・お問い合わせ:TOSSオリジナル教材HP
https://www.tiotoss.jp/products/detail.php?product_id=3654
販売:株式会社教育技術研究所
製作:エンドレスポエトリー株式会社
6.谷編集長の5 min. アンサー
4月号のテーマは
『 デジタル教科書をより活用するには 』です。
こちらは「谷編集長の5min.アンサー」の音声配信です!
音声を聞くには、下の画像をクリックしてください。
7.高段者が答える「私が困っていることQ&A」デジタル版!(動画・音声)
本誌67ページとの連動企画!です。
4月号は林 健広先生
「 4、5月は成功体験させる 」です!
こちらは「TOSS教師に聞く!Q&A」音声配信です! 音声を聞くには、下の画像をクリックしてください。
8.今月のサークル紹介動画
現在はオンライン中心ですが、参加すると元気になる場です
代表者:赤塚邦彦先生 執筆者:赤塚邦彦先生
サークル名:TOSSアツマロウ
コロナ前までは対面でのサークルを月二回行っていました。
一回は何でもありのサークル。一回は授業に特化したサークルでした。
コロナ後はオンライン中心で月二回隔週水曜日に行っています。
四〇分の限られた時間の中で、メンバーの模擬授業、代表である赤塚のミニ講座、
そして、最後は参加者全員の近況報告。この近況報告で皆にお話してもらっています。
近況報告のためにコンテンツを作る強者も!
メンバーのお話を聞き、元気をもらうことができます。興味をお持ちの方はぜひどうぞ!
●教師の社会貢献活動を応援する! 教育コミュニティ●
9.教育コミュニティコンテンツ
①未来ある学生たちへの三つのサポートと一つの共有
ニーズに応える、実演する、縦のつながりを生む。
そして、ぶれない芯を共有する
藤橋 研先生
本誌75ページの関連資料をカラーでご紹介します。
谷氏を囲んで和代表会
1 ニーズに応える
学生たちの、
「こういう授業をしたい」
「こういうことを知りたい」
というニーズに応える。
長らく学生サークルの顧問をしていた谷和樹氏は、かつて次のように語っていた。
勉強さえしてくれていれば、
TOSSでも何でもいい。
未来ある学生たち。彼らが追究したい方向を後押しする姿勢が必要である。
2 実演する
学生たちが模擬授業をする。しつつ、現職が代案を実演する。
やっぱり現職の授業は違う。
これを体感することが憧れを生み、学生たちを成長させる。
3 縦のつながりを生む
学生サークル和(なごみ)は、現在、十七代目まで続いている。
毎年、歴代の代表が谷氏を囲む「和代表会」をはじめ、
「十五周年セミナー」や「学生×現職拡大例会」など縦のつながりを生むイベントを開催している。
学生たちのニーズは多岐にわたる。目指す教師像も、思い描く教師人生も違う。だからこそ、多くのOB・OGたちに出会う場が必要である。
様々な生き方があっていい。
学生が、それを感じる機会をつくるのが、現職の役目である。
4 ぶれない芯を共有する
学生サークル和には、合言葉がある。
「将来出会う子どもたちを幸せにするために」
ぶれない芯を共有していければ、たとえ困難が訪れようとも、
必ず次の世代がつなでいってくれる。
【TOSS Kidsスクール日記】
②TOSS Kids教室七年目の模索
新しいステージで仕事も余暇活動も充実する
TOSS Kids浜松きらりタウン教室
高山佳己先生
一 TOSS Kids教室七年目へ
TOSS Kids浜松きらりタウン教室を開室して、七年目に入った。
現在、三十二人(幼児一人・小学生二十九人・中学生二人)が通塾している。
開室してから現在までの人数の変遷が次である。
「TOSSキッズスクール日記」を執筆するのはこれで五回目であるが、
そのときどきの教室の様子・エピソードや私の思いを記してきた。
□ 開室準備と開室への期待
□ 右肩上がりに伸びていく成長戦略
□ TOSS Kids経営の魅力・やりがい
□ 個人事業主としての新しい経験
などである。
二 ライフスタイルに応じた働き方
現在六十六歳、前期高齢者である。
昨年十一月には、頸椎症性脊髄症の手術で、約一か月間、TOSS Kids教室を休みにした。
健康面、体力面、気力面を考慮に入れた、働き方が重要になってきた。
次年度からは、中学生教室を止めようと思い、
その旨を現在の六年生七人の家庭にアナウンスした。
すると、
「中学生教室をなんとか実施してほしい。」
「うちの子は、TOSS Kidsのような、少数で丁寧に見てもらえるところが合っている。」
「進学指導・受験指導はしなくていいから、教科書の基礎的な内容をできるようにしてほしい。」
という声が、次々と届いた。
心が揺れた。
TOSS Kidsを必要としている家庭がある。
大手進学学習塾にはない魅力を感じておられるのだ。
私は、次のような条件で受け入れることにした。
□特別な、高校入試対策、定期試験対策等は、行いません。
試験・進学対策については、きちんとしたプログラムが用意されている学習塾が
多くありますので、そちらを選択することをお薦めします。
□月曜日・水曜日の十八時~十九時を基本とします。これ以外についてはご相談にのります。
□指導内容は、数学のみです。
・各自の学力に応じて、基礎・基本を中心に、次のテキストを使用します。
・「あかねこ中学数学スキル」
・学校の教科書・問題集の分からないところの指導もします。
□すでに2人の生徒が通塾していますので、新規若干名の受け入れとなります。
このようにしたにもかかわらず、四人の六年生が中学生教室を強く希望し、継続することになった。
ありがたいことである。
☆幼児教室 十五時~十六時
☆小学生教室 十六時~十八時
☆中学生教室 十八時~十九時
これが新しい時程である。来年度の具体的な子供たちの動きは次表のようになる。
三 充実する余暇「俳句の種まき」
TOSS Kidsの利点は、時間的余裕がかなりあることである。
午前中は、フリーである。
午後は、私の場合、十六時(木曜日のみ十五時)~十九時が指導時間である。
三時間勤務である。
前後に合わせて一時間ほどの準備・片付けをするので、実質四時間の勤務となる。
朝ゆとりがあるというのは、現役時代と大きな違いである(NHKの朝ドラを視聴できる)。
心に余裕ができた分、余暇活動が充実してくる。
私は、四年前、テレビ番組「プレバト!!」の夏井いつきさんの影響で俳句作りを始めた。
燕来る動いておらぬ観覧車
蓑虫を手で包む子やまた鬼に
春障子透かしの花の三分咲き
日の多きところへ母の蒲団干す
白露の揺るがず無罪確定す
俳句集団「いつき組」に所属して、楽しく俳句を作っている。
全国的な俳句の大会で入選するようにもなった。
また、井戸砂織先生からご縁をいただき、
豊田市で子供俳句教室や教師向け俳句学習会も行うことができた。
子供たちの言葉を豊かにし、心を育む「俳句の種まき」を地道にすすめている。